日本の贈り物文化において、「おもたせ」という言葉は、特に大切な意味を持ちます。しかし、最近ではその意味や使い方を知らない人も少なくなく、誤用されることもあります。この記事では、「おもたせ」の本来の意味を再確認し、その適切な使い方について詳しく説明します。
「おもたせ」という言葉は、受け取る側が使う言葉であり、客が持参した土産物を指します。昔ながらの使い方とともに、近年では異なる使い方も増えているため、誤解を避けるためにはその違いを理解しておくことが重要です。また、日常生活やビジネスシーンでも活用できる例文を紹介し、より実践的に学ぶことができます。
この記事を読むことで、「おもたせ」の正しい使い方を理解し、贈り物の際により適切な表現を使えるようになります。
「おもたせ」の意味
「おもたせ」の意味について、改めて考えてみましょう。
辞書で調べてみると、
「来客に対して持参された土産物を指し、その品を提供する際に使われる語」とあります。
さらに補足情報として、最近では、客が持参した土産を受け取った側から使うのではなく、例えば「このお菓子がおもたせにぴったりです」のように、客が持参する手土産の意味で使われることが増えているとも書かれていました。
本来、「おもたせ」は、お客様が持参した土産物に対して、受け取る側が使う言葉です。
「おもたせ」の使い方
「おもたせ」の使い方について説明します。
お土産をいただいた相手に対して、その場でお土産を提供する際には、一般的に「おもたせで失礼ですが…」と言うことが多いです。
「おもたせ」の誤用例
- 先日、横浜に行ったので、おもたせとして新鮮な魚を持参しました。
- 結婚式の引き出物をおもたせとしてお持ちしました。お使いください。
- 帰省中に福岡のおもたせをお届けします。
このような使い方は適切ではありません。
「おもたせ」と「手土産」の違い
「おもたせ」と「手土産」を同じ意味だと思っている人もいるかもしれませんが、実は少し違いがあります。
どちらもお土産を指しているのですが、違いは一つだけです。
「おもたせ」は、受け取る側が使う言葉です。
一方、「手土産」は、持参する側が使う言葉です。
つまり、同じお土産を持っていく側から見ると「手土産」となり、受け取る側から見ると「おもたせ」となります。
立場によって使い方が異なります。
ただし、最近では「おもたせ」が「手土産」の意味で使われることも増えてきているようです。
たとえば、「おもたせには、こちらのケーキがぴったりです」といったように、百貨店などの店舗で使われることもあります。
これは本来の意味では誤用ですが、近年では手土産として使われるケースも見受けられます。
とはいえ、この使い方は誤用であることは確かなので、やはり「おもたせ」は受け取る側の言葉として理解しておくべきです。
「おもたせ」と「お使い物」の違いは?
手土産を持参する側が使う言葉に、「おつかいもの」という表現があります。
「おつかいもの」は「お使い物(お遣い物)」とも書き、意味としては贈り物を指します。
「おつかいもの」は、贈る側が使う、少し形式を重んじた贈り物や進物のことを指します。
「おつかいもの」の使い方
百貨店や観光地のショップでお土産を選ぶ際、
「おつかいものですが…」と言ったり、
反対に店員さんから「お使い物ですか?」と尋ねられることがあります。
もしお使い物だとわかれば、店員はそれを包装し、紙袋に入れてくれます。
その際には、熨斗をつけるかどうか、表書きや水引の種類をどうするかを確認されることもあります。
そのため、「おつかいもの」は贈る側が使う言葉であり、「おもたせ」は受け取る側が使う言葉です。
誤って手土産を指す際に使われる「おもたせ」は、実際には「おつかいもの」の方が適切でわかりやすいと言えます。
「おもたせ」のおすすめ文例20選
以下は「おもたせ」の使い方を紹介します。
「おもたせ」の文例
- 「おもたせで失礼いたしますが…」
- 「おもたせですが、お召し上がりいただけますか?」
- 「おもたせで恐縮ですが、どうぞお試しください。」
- 「おもたせで失礼ですが、お召し上がりくださいませ。」
- 「こちらはおもたせとしていただいたものですが…」
- 「ご丁寧におもたせまでいただき、ありがとうございます。」
- 「おもたせで恐縮ですが、どうぞおひとつ。」
- 「これは非常に上品で美味しいおもたせですね。」
- 「こちらは京都の老舗からのおもたせです。以前から一度味わってみたいと思っていました。」
- 「いただいたおもたせ、とても美味しく頂戴しました。」
お使い物・手土産を使った文例
- 「おつかいものには、こちらのお菓子が最適です。」
- 「倉敷でお土産におすすめの品は何でしょうか?」
- 「出張で北海道に行ってきました。こちらは手土産としてお持ちしました。お使いください。」
- 「○○社への初回訪問時に手土産は何が良いでしょうか?」
- 「お疲れ様です、佐藤です。この度はお土産をいただきありがとうございました。チーム一同、大変美味しくいただきました。」
- 「日頃からお世話になっております、田中です。本日はご多忙の中、弊社までお越しいただきありがとうございました。また、手土産まで頂戴し、○○様のお心遣いに感謝しつつ、皆で美味しくいただきました。」
- 「この度はお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。いただいたリンゴは早速部内で分けていただきました。」
- 「おつかいもののことでしたら、当店にお任せください。」
- 「九州に行ってきました。少しですが手土産に博多の明太子をお持ちしました。」
- 「おつかいものを探しているのですが、何が良いでしょうか?」
「おもたせ」についてのまとめ
「おつかいもの」や「おもたせ」という言葉は、あまり頻繁に使われることはないかもしれません。
意味を知っているだけでなく、その存在自体を知らない方も少なくないのが現状です。
最近では、百貨店のスタッフに「おつかいものですが…」と伝えても、経験が浅い方だと「それはどういった意味ですか?」と聞かれることもあります。
その場合には、「贈り物なのですが」と言い換えたり、「プレゼント」や「ギフト」といった言葉を使ったほうが良いかもしれません。
また、「おもたせ」についても、持参したお土産をお茶菓子として出す際に「おもたせですが…」と言われて、何のことか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
ビジネスシーンでも、「おもたせ」や「おつかいもの」のような言葉の使い方を理解しておくことは重要です。
手土産をいただくのは嬉しいことですが、言葉や表情を通じて感謝の気持ちを伝えることも大切です。とはいえ、相手に対しての礼儀を欠くことは避けるべきです。
しかし、前述したように、現在ではこうした言葉を知らない人もいるため、状況に応じて柔軟に使い分けることが求められます。
手土産をいただいた際に、その場でお茶菓子として出すときには、「おもたせで失礼ですが…」と一言添えてみましょう。
「おもたせで失礼ですが…」というフレーズを加えることで、相手に対しての礼儀が伝わり、「この家では来客にお茶菓子も出さないのか?」という印象を与える心配もなくなります。
「おもたせ」をうまく活用することで、贈る側の喜んでほしいという気持ちと、受け取る側の嬉しい気持ちが重なり、共に美味しいひとときを過ごすことができれば、それが何よりの喜びですね。
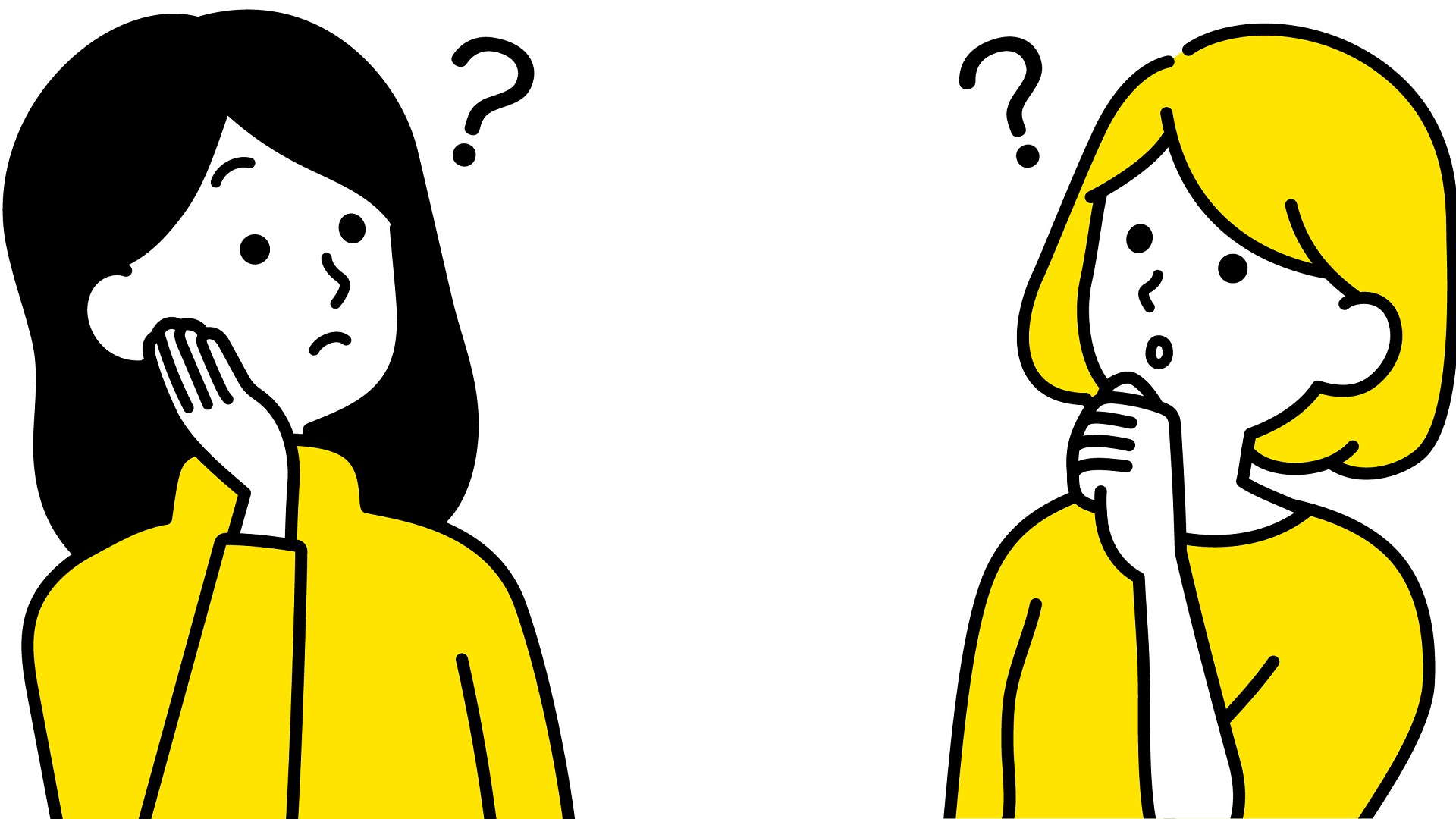


コメント